|
真冬、常葉色の木の根元。 いつだって、一番欲しいものではなかった。 |
 | 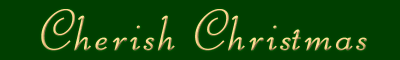 |  |
 |  |
|
「そう、ツリーの星」 店の棚をわざわざ動かしてまで確保した場所に鎮座する、店の広さからすれば大きめといえるツリーを見上げて、遊戯は笑った。 今日は祖父の店は定休日なので、遊戯の他に人はいない。けれど。 『そんなものを欲しいって、言ったのか?』 「あー、何、その言い方?」 まるで――そう、まるで、さながらすぐ傍にいるかのように、お互いが言葉を交わせるようになって。 『だって星って、それのことだろう?』 オーナメントが詰め込まれたいくつかの箱の中で、もう一人の遊戯が意識を向けた、それだけが他と違う。たった一つのための箱だ。 ツリーの一番上に飾る、大きな星。 「うん、最後に天辺に飾る星だよ」 床に足をつけたままでは今でさえ、手を伸ばしたところで指先がかすりもしないほど背の高い、立派なツリーだけれど。 あの天辺でこんな大きな星がきらきら煌めいていたら、きっと綺麗だろう。 『……届かない、な』 脚立はどこに仕舞ってあっただろうか。 「小さい頃の、ことだけど」 『うん?』 「すごくすごく高いところにあったあの星がどうしても欲しくて、取ってもらったことがあるよ」 遊戯の目は、まだ星のないツリーの先に向けられていた。もう一人の遊戯も同じように見上げて、けれど。 「でも。取ってもらった星を、間近で見ても、なんか違うんだよね」 いつからか、自分たちの記憶は微妙なズレを生じるようになってきている。ずっと等しく共有されていたのが、いつの間にか、もう一人の遊戯にとって、自分が発現する以前のことは、記憶にあっても実感が薄れて。それはお互いがお互いの、自分であって自分でない時間を感じるのと似ていた、けれど。 『違う?』 「うん。違ったんだ」 一つ頷いて、遊戯はおかしそうに笑った。 「だって、ツリーの上にあった星じゃなかったから」 まるで言葉遊びのようだけれど。 『……そうだな、それは確かに別物だぜ』 今なら、この手はどこに届くのだろうか。 |
|
「夢を、見たんだ」 その夢の中の自分は幼くて小さくて、何もないところに一人で立っていた。 埋もれそうな雪の街中だった。 音もない街で、独り、立っていた。 とてもとても悲しくなって、泣いていたら。 ――誰かの手が、差し出された。 |
|
「よーっす…って、何やってんだ? 遊戯?」 店のドアをくぐって真っ先に城之内の視界に飛び込んできたのは、脚立を肩に抱えた遊戯の姿だった。 「飾り付けだ」 「ぁん?」 遊戯が目で指す、棚で死角になってしまっている位置を見るために駆け寄ってみると、陳列棚が除けられて広くなっている空間に悠々と鎮座する、 「クリスマスツリー、か」 しかもなかなか大きい。城之内より頭一つ高いぐらいもあれば、遊戯の背なら確かに脚立を持ち出さねば届かないだろう。それを口に出して言えば、今の遊戯でもきっとむくれてしまうだろうが。 「じーちゃんに頼まれてな」 ツリーの傍らに脚立を広げ、オーナメントを詰め込んだ箱を小脇に登ると、遊戯は脚立のてっぺんに座り込む。 「へぇ……こりゃ立派なもんだな」 店内の皓い照明の光を弾いてきらきら輝くモールが、上からゆるりと巻き付けられて。こまごまとした物が枝につるされて、そこかしこには雪を模した白い綿が添えられて。 「昔ヨーロッパで買ったらしい、自慢の品って言ってたぜ」 だいたい枝の部分の下三分の一程度が、そんな色とりどりのオーナメントで飾られていた。 「おまえのじーさんって行動範囲広いのな」 「だからこそ、パズルも手に入れたんだろうがな」 「違いねぇ」 と。着々と遊戯の手によって進められる飾り付けを眺めていた城之内の脳裏に、ふとハテナがよぎる。 少しだけ考えて。目の前のツリーと、横手の脚立と、自分の身長を確かめて。今は脚立の上にいる、遊戯の身長を思い出して。 そういうことかと思い至った答えに、気づかれない程度の苦笑を添えると、遊戯が座る天辺の段より一つ下に置かれている、オーナメントの箱の一つをさっと取り上げた。 「城之内くん?」 「オレこういうの、したことねぇのよ。ちょっとぐらいやらせてくれって」 床に立った遊戯の手が届く位置と、脚立の一番上から危なげなく手が伸ばせる範囲との、中間辺り。ちょうど城之内に手頃な場所が、他と比べてオーナメントが目立って少ない。 「……すまない」 ああ、ばれたかな。軽く笑って、城之内は流した。 全体を見渡しながら、残りのオーナメントをバランスよく配置する。手に取って気づいたが、オーナメントはずいぶんと正統派らしい。くすんだ常緑の色も相まって、街中で派手に輝くツリーとは一風違った、落ち着きある古めかしさが感じられた。 「そういや、あっちの遊戯は?」 「相棒なら下の方を飾り付けた後に交替したぜ。……初めてなんだからやってみろって」 「初めて?」 思わず反復する。 つと、遊戯が脚立の上で腰を浮かした。重心が変わったことで、ごく微かに軋む音がして、咄嗟に支える。 「オレがオレで在るという意味で、初めてのクリスマスだ」 ツリーの天辺に、大きな星がそっと飾られた。 |
|
「夢を、見たんだ」 その夢の中の自分は何も見えなくて、知らないところに一人で立っていた。 ただただ真っ暗な街中だった。 光もない街で、独り、立っていた。 とてもとても恐ろしくなって、走り出したら。 ――誰かの声が、聞こえてきた。 |
|
もう随分と昔のことだ。 「じーちゃん!」 近づいてくる姿を見つけた瞬間、遊戯はコートの裾に飛びついた。 「あのね、おかえりー」 「おお、遊戯、わざわざ迎えに来てくれたのか?」 そのまま一気に抱き上げられて、どこからともなく取り出された、黒いつなぎを着て黒いシルクハットをかぶった人形を渡される。 「何、これ?」 「煙突掃除人形じゃ。ま、幸せのお守りみたいなもんじゃの」 「うん? ありがとうー」 双六は今でこそ遠出を控えているが、昔はよく長い間いなくなっては、世界中から不思議な物をたくさん持ち帰ってきた。それはいつもいつも、趣味の珍しいゲームばかりというわけではなくて。毎年店に飾っているクリスマスツリーも、同じ年にドイツで見つけてきた物だった。 「いい子にしとったか? ママを困らせたりしとらんかっただろうな?」 今年幼稚園に入ったばかりの年とはいえ、双六ももう遊戯と荷物を抱えていくわけにはいかない。地面に下ろして、手をつないで家路を歩く。 「ちゃんと来たよ、サンタさん!」 無邪気に顔を輝かせて笑う遊戯に、双六も破顔する。と。 「そうかそうか。欲しい物はもらえたか?」 ふっと遊戯が笑顔を引っ込めたので、眉をひそめた。 「なんじゃ、どうした?」 「あのね、欲しかったけど、違うの」 一番の願い事が。 「そうか」 「お星様と一緒だね」 そう言った遊戯が、ふいに立ち止まる。 「……雪か。寒いわけだの」 空を覆うグレーの雲から、はらはらと白い雪が舞っていた。 「知っとるか? 初めての雪を手のひらに受け止められたら、願い事が叶うんじゃぞ」 雪は雫に溶けて瞬く間に消えてしまい、広げた手のひらには何も残らない。遊戯に、祖父は笑ってそう言ったのだ。 「じゃあね、会えますようにってお願いする」 「誰にじゃ?」 「んー、……わかんない」 いつだって、一番欲しいものではなかった。 だったら何が一番欲しかったのか、なんて。 その頃にはまるでわかっていなかったけれど。 その日も、クリスマスだった。 |
|
真冬、常葉色の木の根元。 いつだって、一番欲しいものではなかった。 ――今だからわかること、だけれど。 |
|
「うわ、寒!」 吹きつけた風の、その鋭い冷たさに、遊戯が身をすくませる。 『陽が低くなると本当に冷えるな……』 「十二月ももう終わり頃だしね」 何の用事もなければ、こんな時期こんな時間、わざわざ出歩きたくなんてないけれど。 学校指定の色が暗いコートに映える、白のマフラーは前の冬に母が買ってきた物だったか。少し緩みかけていたそれを、遊戯は貴重なぬくもりを逃がさぬように巻きなおす。 「ああでも、雪でも降りそう……」 いっそ降ってくれればホワイト・クリスマスだけれど。 見てるだけでも寒々しいグレーの空を、見上げてつぶやいた。と。 『確かに、見てるオレまで寒くなってきそうだぜ……』 「……」 はたと遊戯が立ち止まる。 『相棒?』 「そっか、そういうことだったんだね」 『何が――』 急に遊戯が浮かべた、張りついたような笑顔を訝った、刹那。 「って、いきなり――!」 隙をつかれて交替させられた、もう一人の遊戯が慌てふためき言いかけた言葉は、しかし途絶えた。 『何、どうしたの、もう一人のボク?』 「……寒い。寒すぎる。相棒、もう少し着込んできた方がよかったんじゃないのか……?」 思いっきり身を縮こまらせてささやく、その声は懇願にも近いように聞こえたけれど。 『まだ十二月だよ、今からそんなこと言ってたら、冬本番の一月や二月はどうするんだよ』 「空気が乾いてるのが悪いんだな、夏は嫌味なくらい湿気ているくせに……」 いつも無意識でも凛と背筋を伸ばしているもう一人の遊戯が、恨みがましくつぶやきながら、さながら猫のように背を丸めている、これはこれで珍しい。 思わず遊戯が失笑すると、拗ねたように苦い顔を返された。 何の用事もなければ、こんな時期こんな時間、わざわざ出歩きたくなんてないけれど。 『ほらほら早く! 約束の時間に遅れるよ!』 なんたって御招待の集合時間だし。 『それに、向こうに着いたらきっと暖かいよ!』 なんたって海馬くんのあの家だし。 「わかってる! というか相棒が昨日買い忘れしなけりゃオレたちは家で待ってるだけでも……」 海馬当人は仕事が忙しく不在だし。 『ああ! 言っちゃいけないことを言う! それ、みんなにまで言ったら許さないからね!?』 「………………ああ、わかってるぜ」 気づいていながら海馬のこととなるとなぜか腹が立って言わなかったのは、自分だし。――とは、口には出さずに飲み込むけれど。 『じゃあ、走る走る!』 「まだバスの時間までなら余裕が」 あるだろう、と続けるのを、もう一人の遊戯は思わず忘れる。 童実野駅前の広場には、樅の木があった。まだ若いが、それなりの高さもあって、いつの年からかライトアップされるようになっていた。 その灯火が、今、目の前でぱっと入った。 一番星が、ツリーの上にきらりと光った。 小さな白い雪が、空からはらりと降った。 |
|
「夢を、見たんだ」 その夢の中で、二人は手をつないで、一緒に歩いていた。 たくさんの人と出会う街中だった。 幼く小さな子は、何も見えない子に守られながら、大きくなっていった。 何も見えない子は、幼く小さな子に守られながら、世界を知っていった。 |
|
真冬の空の下、星を飾った、常葉色の木の根元。 ふわりふわりと雪はひとかけら降っただけで、消えてしまったけれど。 「綺麗だな」 舞い降りた最後の一つを、思わず手のひらですくいとる。うっすらと残る、先ほどまで雪だった雫。 『願い事』 「え?」 『初雪をつかまえたら、願い事が叶うって』 何年も前、十年以上前、初雪を見た。 「その時、相棒は何を願ったんだ?」 あの雪の日、空を仰いで。 『会えますように、って』 「誰に?」 『ボクもわからない』 けれど。 『けど、きっと、……ずっと、願ってたんだ』 君と会えること。 |
|
「夢を、見たんだ」 その夢の中で、ふと、振り返った。 とてもとてもよく知っている、笑顔だった。 |
|
『メリークリスマス、もう一人のボク』 不意打ちだった。 「……なんで、城之内くんが、……え?」 いきなり渡された小さなプレゼントを両手で持って、呆然と立ちつくしている様はきっと、端から見れば滑稽だったに違いない。 「あー。おまえにばれないように、オレが用意を頼まれましたってオチで」 『そういうオチで』 「……そういう、オチか」 だったら。 ――笑ってしまおう。思いっきり。 |
|
クリスマス企画SS。雑記で没と出した部分も、しっかり復活して入りました(笑) なにはともあれ滑り込みセーフ! いえ11月末(ツリーは11月最終週に出す習慣だったはず)〜12月25日ネタなので。これでイヴ物だったらそんな遅刻じゃないですか平謝り物です。 わかりにくそうで、すみません。 補足。「常葉色」は「ときわいろ」と読みます。 2001.12.25. |