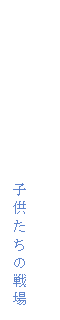 |  |
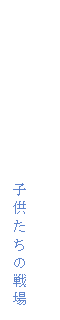 |  |
|
肉を斬れば、刃は血と脂にまみれた。 積み重なる死臭に、魂なんて見えなかった。 転がる骸の表情はいつも苦悶に歪んでいた。 もう何も映さない濁った目が、恨んでるようで。 ――少し、ぞっとした。 |
|
狭い世界を覆っていた、幼く優しい幻想が剥ぎ取られたら。 あまりに広い世界の中で、あまりに小さすぎる自分は途方に暮れた。 |
|
戦場を生きて、駆け足で子供時代を終えたように見えても。 本当は、大人びただけの子供でしかないのかもしれなかった。 今更そんなことを思う。 けれど、今だから思うのかもしれない。 |
|
小さな小さな手。短い短い腕。 それで抱きしめ守れるものなんて、いくつあるのだろう。 |
|
子供、子供と、大人たちは言うけれど。 何を指してその境界線は引かれるのでしょうか。 |
|
無邪気に蟻を踏みにじった日々は過ぎ去って。 死を厭う面持ちを張りつかせながら人を殺す。 諦めることを覚えたら、大人になれるのでしょうか。 |
|
無邪気にすべてを望めなくなったのは、いつからだったろう。 甘い幻想を諦められるようになったのは、いつからだったろう。 見知らぬ人を殺すことにも諦めたのは、いったいいつだったろう。 たくさんの命を奪って。 たくさんの命を喪って。 たくさんの死を知って。 ただの子供のままではいられなかった、それでも。 やわらかに笑う、そんなあの人が、大好きです。 こんな褪せない信も、幼く甘やかなのかもしれないけれど。 |
|
この長い重い話を最後まで読んでくださってありがとうございます。 幻水でじっくり重い話を書くのは久しぶりでしたが、書き始めに考えていた物よりも、出来上がりは遥かに重くなりました。タイトルが[子供たちの戦場]に決まった頃からでしょうか、もともと思っていた、フッチとサスケが友達関係築くまでの話というだけでなくなったのは。 それで、いつもはテーマをわりと水面近くに出して物語っているつもりですが、今回はたぶんずっと深いところに沈んでると思います。明言らしい明言は避けました。 願わくば、万華鏡のように読み込んでいただけると物書き冥利に尽きます。でもってその想いを、一言でも構いませんので私にもお教えくださると感激です。 |