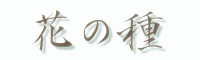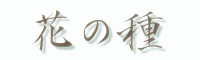──心にあく穴を埋める 土があるなら そこに種を落とし 育てゆく術もある?
angela「Proof」より
昔の記憶は、ひどく曖昧だった。
一般的に子供と呼ばれる年頃のものは殊更に断片的で、思い起こせる限りの中に両親や故郷のイメージはなかった。子供の頃にどんなことがあったかも、自分がどんな子供だったかも、ほとんど覚えていない。ただ円の宮殿の一角で、白い部屋の中で、数人の養育係としか顔を合わさない生活をしていた。未来の神官将として嘱望され、あらゆる面で高等教育を施されていた。
それだけの、ひどく狭い世界だった。
そして、そのことに疑問を持つこともなかった。他の、普通の子供がどうかなど、まったく知らなかったからかもしれない。同年代の子供に会ったことすら、ただの一度もなかった。
しかし、いったい自分は誰なのかと、一度も考えたことがないわけではなかった。
あれは確か、十といくつかを数えた頃に。
神官として少しずつ実務にも携わるようになり、養育係以外の人間と接することも増えだした頃に。その周囲の人間たちには家族というものが存在することを、親と子という概念を、初めて目の当たりにした頃に。
自分をこの世界に生み出した存在、親は誰なのか、まったく知らないことに初めて気づいた。見たことも聞いたこともない、しかし存在するはずの人間を、自分から抜け落ちている自分のルーツを、その瞬間、初めて知りたいと思った。
かつて養育係でもあった世話係の男に訊ねて、自分は生まれたばかりの頃から円の宮殿で育てられていたことを、初めて知った。しかしそれ以上のことを一介の世話係が知るはずもなく、神官の人事を管理している場所に入り込んで、自分の経歴を盗み見た。
そこには、さして珍しくもない男と女の名前と、聞いたことのない地名と、十数年前の日付が記されていた。
「こんな物で、昔の私は納得していたんだな」
もう、こんな物を二度と見ることはないと思っていたけれど。
あの時に見たものより文章量が増えているのは、あれから二十年という歳月が流れたからだ。だが、自分の名前に添えられた生年、出身地、両親の名前。それだけは、あの頃とまったく変わっていない。
この僅かな量の文字を見ただけで、幼い自分は納得したのだ。
満足、していたのだ。
所詮は好奇心に過ぎなかった。親という存在は少しの実感も伴っておらず、自分の世界のすべては円の宮殿の中だけにあった。ただ適当な答えさえ与えられていれば、それで良かったのだ。何も知らないことに、自分の存在そのものに不安を覚えるようなことなど、なかった。
愚かしい過去の自分に、羨望すら覚える。
たといこのありふれた名前を持つ男女がいたとしても、この書類に記されている男女は何処にも存在しないだろう。
そう、存在しない。
ササライという名の子を産んだ、夫婦など。
この世界の、何処にも過去にも存在しているはずがない。
──だって自分は、産まれずに生まれたから。
高い山も木もない、大きな建物もない。
何もない、草原の空は広すぎる。
唐突に思って、そう思ったままを口にすると、花の種が入った袋を持っている少年は笑って、おっとりと笑って、僕も初めてグラスランドに来たときは吃驚しましたと同意を口にした。その声が嬉しそうに聞こえて少し首を傾げると、綺麗な空は気持ちがいいから好きですと彼は続けた。
綺麗な、空。
胸中で繰り返しながら、真上の空に目を向ける。
それから、君はここの出身ではなかったんだねと問い返すと、彼は何度か目を瞬かせたが、ああ、とすぐに得心したように肯いた。そして、母と無名諸国で暮らしていたんですけど、母が他界してしまったんで父を訪ねてゼクセンに来たら、この城に厄介払いされちゃったんですと苦笑いした。
咄嗟に庶子と呟いてしまって、すぐに非礼を詫びても、でもその通りですからと困ったように笑う。
穏やかに、やわらかに。
小さな花の種を一つまみ、はらりと土に落とす。
だから。
父親を憎んでるかいと問うたのは、おそらく意地の悪さが囁いたからだろう。
さすがに少し驚いたように目を見張った彼は、少し悩んだように視線を彷徨わせて、やはり苦く微笑んだ。そうして返ってきた答えは、否定の言葉ではなく、よくわからないという言葉。父親とは一度しか会ったことがなくて、会話すら、まともにしたことがないからと。それから視線を滑るように落として、これからもすることはないでしょうしと呟く、その笑い方は寂しげに見えた。
少しだけ、苛ついた。ざわざわと音を立てて。
最初から会わなければよかったと思ったことはないのと口にした自分の声が、いやに低く聞こえた。
目を閉じれば瞼の裏で、自分を兄と呼んだ瓜二つの顔が、見たこともない強烈な激情に彩られていた。
とてつもなく激しい感情に。
いつか自分も、あんな怒りを抱くのだろうか。
彼のように。
「たぶん、まったくないわけじゃありませんけど、でも」
それでも。
「父に会ったから、僕は今、此処にいるんですよね」
やはりおっとりと微笑んで、トーマスは答えた。
そんな彼の言葉と表情に覚えたのは、ひどく不可思議な感慨だった。
「運命、か……」
そう自嘲気味に呟いたら、彼は少しだけ戸惑って、だが何も言わずに微笑んだ。
ひどく穏やかに、とてもやわらかに。
「これ、綺麗な花が咲くんです」
もう一つまみ、はらはらと、小さな花の種を黒い土に落とす。
「春が始まる頃に」
綺麗な、花。
思わず目を細めて、視線を彼から外した。
真の土の紋章がなくなった、空っぽの右手に目を落とした。
ぽっかりと空きすぎてしまった穴を、持て余しているだけだった。
その穴を埋めるものなど、自分は何も持ってはいなかった。
だから。
「その頃には、きっとこの戦争も終わっているだろうね」
どうして彼は、あんなに激しく生きることが出来るのだろう。
訊いてみたいと、知りたいと、ササライは初めて思った。
ササライ。と、トーマス。
うちのサイトではグラスランド争乱は、[Meridian Child]でも触れてますが秋の出来事。
夏が終わった後の秋。冬の始まりに遠い春を待つ。
春が始まる頃には、もうここにはいない。
トーマスはとてもやわらかで、とても逞しい人。しっかり地面に足がついていて、危うさのない人。冬を乗り越えて、春を迎える人。春の初めに咲く花は、桜草。花言葉は希望。青春の始まりと悲しみ。
ササライは保管庫扱いのルックと違って表面上は人間扱いされていそうでも、ある意味で究極の温室育ちみたいな感じで。個人的には二人は「生まれたときからあの姿」説です。自分の姿とか鏡も写真もなければ意識することもなく、他の子供もいなければ他と違うと気づくこともなく、成長してしまえば幼少期の記憶は曖昧すぎて、知識と常識が都合良く埋め合わせてしまう。
言われて振り返れば、自分が立っていた世界は、まやかしだった。
IIIのルックの、あの怒りの原動力は何だったのだろうと思います。
何かに激しい怒りを持つのって、持ち続けるのって、とてもエネルギーがいるじゃないですか。
怒るということは、現実と思い描いた理想や願望との間に、許し難い隔たりがあるから。
自殺に高尚な御為ごかしは要らない。死への強い欲望と衝動さえあればいい。
だから物語は『道、別たれて』に続きます。