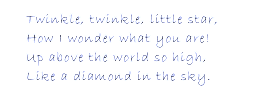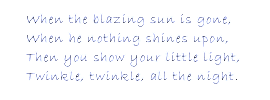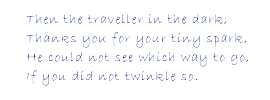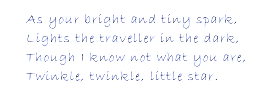覚えている。いつまでも。たとえ彼女が、二度と振り向かなくても。
Twinkle, twinkle, little star
〜ちいさなひかり〜
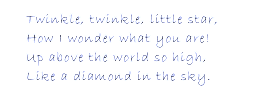
最上階のベランダの手摺りから身を乗り出しながら、アッシュはその一点から視線を外せなかった。
遠く眼下に見える聖堂前の広場、石碑の傍らに、小さく小さく彼女の姿が見える。
彼女がいる。
「アッシュ、何、見える?」
つと隣に寄ってきた、アリエッタが不思議そうにアッシュを見上げてくる。その後ろには彼女の家族であるライガが伏している。
アッシュはその素性故に、アリエッタはその家族故に、あの場所に行くことが許されない。
「ああ、ナタ──いや、イオンがいる」
目線だけでアッシュが広場を指し示すと、すぐさま彼女の注意はそちらへ向けられた。
「イオンさま!」
それだけでぱっと笑顔になるアリエッタに、僅かに苦い笑みをこぼして、アッシュも視線を戻した。この場所から離れられない自分も、似たようなものだ。
聖堂前で、エベノスの代からの導師守護役のみを伴ったイオンが、石碑巡礼のために来訪した彼女と、談笑を交わしている。ここからでは遠すぎて、はっきりとは見えないが。
キムラスカ・ランバルディア王国の王女である、彼女と。
しかし挨拶だけならまだしも、詠師ではなく導師が巡礼に同道するなど、賓客が国王その人でもない限り滅多にあることではない。イオンは彼女と年の頃が近いことなどを適当に並び立て、いつもの調子で周囲を説き伏せてしまったらしいが、本当の目的は、すべてが決まってからようやくアッシュに知らせた時の、彼の表情が物語っている。どんな方か一度お会いしてみたかったなどという台詞も半分だ。
二年も顔をつきあわせていれば、わからないはずがない。
「……嫌がらせか、あの野郎」
吐き捨てた呟きは、拗ねたような情けない響きだった。
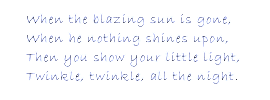
あれから二年が経った。
少しだけ年上だった彼女は、記憶にあるより少しだけ大人になっていて、記憶にあるよりずっと綺麗になっていた。
この目で見える彼女の笑顔は、ひどく遠い。
「アッシュ」
「──っ、おい、引っ張るな」
ぐいと長い髪を引かれた痛みで、アッシュは我に返った。アリエッタの指に掴まっている紅い髪を引き抜いて、嘆息を落とす。
こんな思考は詮無いことだと、わかっている。ルークでなくなるということはそういうことで、アッシュになるということはそういうことなのだ。わかっている。わかっていて、ここにいる。
だから、これはきっと未練などではなくて。
「アッシュ、何、見てる?」
「だから」
未練などという、そんな言葉で済ませられるようなものではなくて。
「イオンさま、いる。アリエッタはイオンさま見てる。アッシュは?」
「……イオンと一緒にいる、あの」
逡巡の末に呟くような声で答えると、ぴったり身を寄せてきたアリエッタが、アッシュの視線を辿るようにして目を凝らす。
「どれ?」
「……金髪の」
「それ、ふわふわ?」
「この距離で、よく見えるな」
「うん」
振り返ったアリエッタが、肯いて笑った。
「笑ってる。あれ誰?」
輝かしく晴れやかに。彼女はきっと、今も。いつまでも。
「ナタリア」
いつまでも、彼女は彼女のままでいるだろう。
「……ナタリア」
「そうだ」
「行かないの?」
今なお在り続ける彼女への想いは、未練などという、そんな言葉で括れる感情ではなくて。
だから。
「会いたくても、会ってはいけない時もある。どんなに会いたくても、今は、会うわけにはいかないんだ」
自分自身に言い聞かせるように、アッシュは一つ一つの音をはっきりと声に乗せる。
それを聞いたアリエッタはきゅっと眉根を寄せ、ひどく苦い表情で黙り込んだ。アッシュの言葉に納得できないのだろう、だが反論するための言葉を持たない彼女は、ただ否定の感情だけを無言で表す。
「いつか、おまえも、それをわからなければいけなくなる」
「……アリエッタ、わかんない」
消え入りそうな声で拒絶だけを口にしたアリエッタの、頭を一度だけアッシュはくしゃりと撫でた。
あと三年で、この微睡みの夢のような日々は終わる。
それは、いつかなどという曖昧に予定された未来ではなく、確定された未来の事実だ。
あと三年でイオンが死んで、あと五年でアッシュとアリエッタが死ぬ。
最後まで生き残っているのは、どちらだろう。
ふと、アッシュはそんなことを思った。一瞬だけ、そう思った。
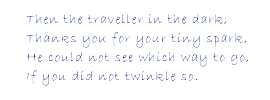
あれから二年が経った。
少しだけ年上だった彼女は、記憶にあるより少しだけ大人になっていて、記憶にあるよりずっと綺麗になっていた。
彼女の記憶にある『ルーク』は二年前のまま、今も変わらないのだろうか。
それとも、彼女の記憶は、すべてレプリカとやらに塗り替えられてしまっただろうか。
「とても綺麗な人でした」
「当たり前だ」
即答ついでにアッシュが満面の笑顔に向けて枕を投げつけると、それはあっさり受け止められた。
「何するんですか」
「八つ当たり」
「ひどいなあ」
ぽんぽんと軽い枕を何度も真上に投げながらイオンがぼやく。それでも顔は笑っている。
「……何が言いたい?」
跳ねていた、枕の動きが止まる。
「聞きたいですか?」
「はぐらかすな」
「実は、ナタリア王女とお話ししていたときに、ルークの話になりまして」
さんざん勿体ぶられたイオンの話に、ナタリアの名前に、思わずアッシュは身を乗り出した。と、唐突に視界が白い色に埋め尽くされて。
「おまえな……」
ぽすんと落下した枕の向こうで、投げた姿勢のままで、睨みつけたイオンはやはり笑顔だった。
「どんな約束をしたんですか? ナタリア王女と」
「誰が言うか」
「でしょうね、残念」
そう言って肩を竦めたイオンの笑顔が、刹那、色を変えた。
「ナタリア王女は、ずっと待っていると言っていました」
「待っている?」
問い返した、声が震えたのがわかる。
イオンは笑って肯いた。
やわらかく笑って、言った。
「いつか、ルークが約束を思い出す日を。そしてその日が来た時のために、自分は約束を守り続けると」
「──ナタリア」
それに、何と言えばいい。それに、何を思えばいい。
「とても綺麗な人ですね」
もう一度、イオンが言った。
「当たり、前だっ……」
嗚咽のように喉が引きつれたが、涙だけは意地でも堪えた。
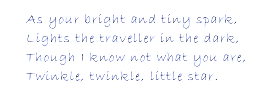
愛している。いつまでも。たとえ彼女が、二度と振り向かなくても。
お題no.13「涙の痕」。
もう、泣いたから。もう、泣かない。
日没までを数える、長くて短い夕暮れ。
死の預言のために真昼を奪われた子供たちが、涙を拭って見上げる、光。
ヴァンはイオン様にちゃっかりバチカルへ追いやられています。監視はお仕事ですから。