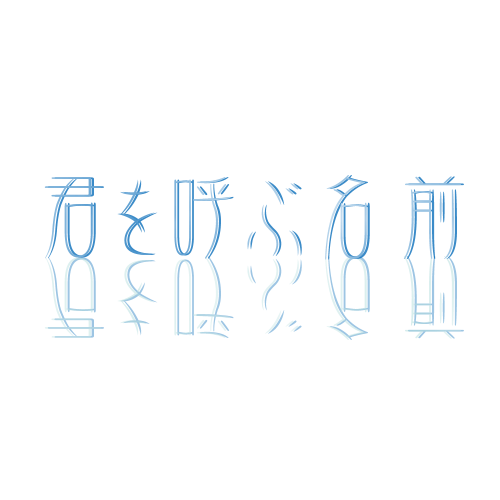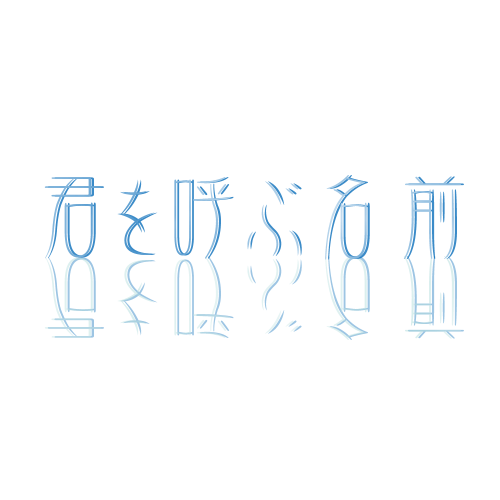──What's in a name?
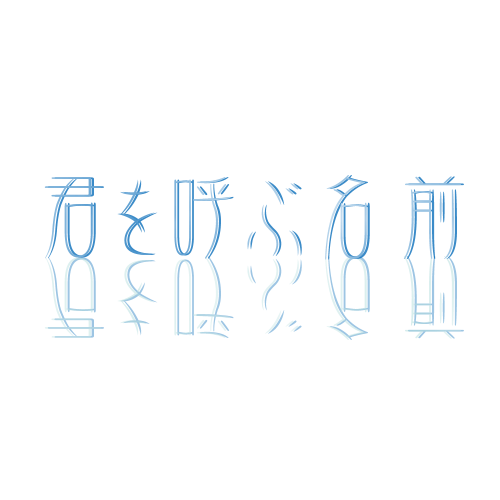
名前には意味がある。
命名は生まれた文化に根ざしているものだ。親から受け継ぐファミリーネームはもちろんだが、キリスト教の文化圏出身者ではやはり聖書や聖人ゆかりの名前が根強いというように。
カリウの出自の手掛かりになり得るのは、カリウという音を持った名前の他には、あとは顔立ちくらいのものだ。髪の色や虹彩の色は生身のそれとは違うのだろうと思っている。
現在セントラルライフはその最も重要な人類の復元機能に関して続報がまったく公開されていないが、回収されたデータベースの整理は順調らしく、蔵書データも順次公開が進められている。その内訳は世俗的な本から高度な学術書まで多岐に渡り、乱読家のルーなどは目を輝かせて日々端末にかじりついているし、カリウも暇を見ては地球の地理や文化関係はチェックしていた。
過去の記憶がないことにもだいぶ慣れたが、自分の素性がどうでもよくなったわけではない。地球のことを何か欠片でも思い出せれば、引っかかりを感じられれば、それが自分を捜す手掛かりになるかもしれない。
それに何かと異星人との交流が多くなって、地球の文化は知識だけでも押さえておきたいところだった。たとえカリウに実感は伴わなくても、それは地球の中の異文化でも同じことのはずだ。
この本も、任務の合間にライブラリの目録を物色していて見つけたものだった。
――名前辞典。よく使われる地域や、言語によって変化する綴りや発音、名前の語源などがまとめられている。
「カリウさん。難しい顔で何を見てるんですか?」
ひょいとカウンターテーブルの反対側から身を乗り出してきたリンの声で、カリウははたと我に返った。
「そんな顔してたか?」
「はい。つまんなそうな顔してました」
答える代わりに、カリウは名前辞典の表紙画面を彼女の前に差し出した。
「名前辞典……? どうしたんですか、それ」
「公開ライブラリの新着リストで見つけて、ちょっと面白そうだなと思って落としてみたんだが」
「面白いんですか?」
「それなりに」
こてんと首を傾げた少女の名前Lynleeを検索すると、すぐに掲載ページが見つかった。
「あ、私の名前! 普通の人の名前にも語源とかあるんですね。私のは湖って意味なんだぁ」
「リンの名前はイギリスのウェールズの言葉から来てるんだな」
「私も初めて知りました。これって、私のお母さんの方のご先祖様がイギリスから来てるかもしれないんですよね」
「関係なく有名人からもらっただけかもしれないぜ?」
「ワールドワイドに有名ならきっと何か言われます。ローカルならきっと地元です」
そう言ったリンは上機嫌で、今まで不思議そうな顔で成り行きを見ていたタツも、よくわからないなりに面白いもののようだと思ったらしい、弾むような勢いで飛びついてきた。
「タツは、タツの名前は何ですも!?」
「タツ? それらしいのはないなあ、残念だが」
「そんなぁですも……」
「当たり前でしょ、地球の本なんだから」
ぐにゃりと潰れるように落ち込んだタツの姿に、リンは呆れ、エルマはくすくすと忍び笑いをこぼした。
「名前も文化の一つよ。地球人の名前、ノポン族の名前、マ・ノン人の名前、バイアス人の名前、オルフェ人の名前、ザルボッガ人の名前、みんな雰囲気が違うでしょう」
指折り数えながらエルマが並べていく。
「その本は地球にあった国の一つで作られたものだから、地球でよく使われる名前しか載っていないの。それに地球は、地球人の中だけでも地域によって文化も言葉もいろいろ分かれているから、その本に地球人全員の名前が載っているわけじゃないはずよ」
「ああ確かに、この本、ヨーロッパ系がほとんどだわ」
もともとはアメリカで出版された名前辞典だ。付録的にアジア系や中東系、アフリカ系も多少収録されているが、辞典と呼べるレベルではない。他にそういった地域の名前を専門にした辞典があるのかもしれないが、現在公開中のライブラリにはあいにくと見当たらなかった。
「じゃあ……えっと、ナギおじさまはないんですね」
「そもそも長官の名前の漢字がわかんねえ」
「あ、そっか」
漢字は表意文字だ。字一つ一つが既に意味を持っている。
「ないのはタツだけじゃないですも?」
「だな。俺もないぞー」
「カリウさんもないですも? お仲間ですも」
「タツの名前の由来は、ノポンの中で調べなきゃね。タツが生まれたときにお父様とお母様が考えて名前を決めたはずよ、今度訊いてみたらいいんじゃないかしら」
「そうしますも!」
「それいいですね!」
それは名案だとタツは顔を輝かせて小躍りする。リンもすっかり乗り気なので、明日にも二人でドドンガキャラバンに出かけていきそうだ。
「ナイスフォロー」
「どういたしまして。で、あなたはその本で自分の名前を探していたの?」
微笑みながら問い返してきたエルマの声には、わずかに気遣うような色が滲んでいる。その結果が芳しくなかったのも見抜かれているようだとカリウは苦笑いを返した。
「正確な綴りもわかんねえからな、それらしいの当たってみたんだか空振りだ」
「カリウの名前は普通のアメリカ人とは少し違う感じだものね」
今のNLA市民登録に用いているカリウの名前のスペリングは、アメリカ英語風に作った仮のものでしかない。
「他の人にも訊いてみたら? あなたの思いも寄らない綴りを思いつく人がいるかもしれないわよ」
「そういうのもありか」
「いろいろ試してみなさい。駄目だったとしても、その本一冊で白鯨のクルー全員を網羅するなんて不可能というだけの話よ」
「わかってる。もともと半分遊びのつもりです。でも意外とエルマの名前はあるんだよなあ、これ」
しかも男性形はキリスト教の聖人の名前だ。オーソドックスだ。
「そうなの? 地球でも同じような音の言葉があるなんて、不思議だけど面白いわね。どんな意味かしら」
「愛すること」
一瞬、彼女の瞳が大きく揺らいだ。
「えっ、フライってFlyって書くのか!?」
思わずテーブルの隅に置いた端末に打ち込む、カリウの指が止まった。
翌日、偶然行き会った非番仲間のクリストフ兄弟とイエルヴとで少し遅い昼飯にダイナーになだれ込み、リンとタツのNLA外出理由から名前辞典の話に及んだのだが。
「そうだよ。おまえだって何度も見てるだろ」
「臨時チーム組んだ時のメンバー登録? いちいち見てねえよ。でもさあ、それ……飛ぶっていうか……」
名詞のflyは、別のものが先に思い浮かんでしまう。
「ああ! アイルランドの虫野郎!」
言葉を濁すカリウの隣で、首を捻っていたイエルヴが思い出したとばかりに勢いよく言い放った。ご丁寧にも向かいに座るフライを指さして。
「よしイエルヴてめえも殴られたいらしいな」
「え? あ! いや違ぇし! あんたじゃねえ!」
これ見よがしにフライが拳を鳴らすと、途端にイエルヴが泡を食って手と首を勢いよく横に振りながら悪意がないことを訴えるが。
「もちろん、映画の台詞だってのは、俺もわかってるぜぇ?」
身を乗り出して上からがっちりイエルヴの頭を鷲掴みにしたフライの指に、結構な力がこもっているのが傍目にもわかる。
「そう! 映画だよ! 思い出したらつい声に出ちまっただけで! なあ相棒も何とか言ってくれよ……!」
ここのように奥まった席を取ってしまえば、多少ふざけて騒いでも店内の喧噪に飲み込まれるのがダイナーの楽なところだよなあとカリウはイエルヴのヘルプを聞き流し、テーブルの上の空いた食器をまとめて空席に寄せる。手伝うフォグも当然まったく耳を貸さない。
「フォグも霧のFogと同じ?」
「そうですよ。あの映画って今NLAでやってるんですか?」
「いやどうかな、俺らは個人で上映会やってるチームをダグに紹介してもらったんだ。俺も映画とか全然わかんねえから」
「そんな連中いたのか」
フォグだけでなくフライもそれは初耳だと目を瞠る。ついでにフライの手が緩んだ隙に抜け出したイエルヴが、カリウの反対側の隣席に逃げ込んできた。これで六人掛けテーブルの対角線だ。フライもそこまで追いかけたりはしない。
「俺も最初はマ・ノン船のサロンで上映会やる企画の手伝いだったんだけどさ。結構楽しい」
上映作品は大衆向け名作で当然面白いし、ついてきたイエルヴもそれこそマ・ノン人と同レベルで笑って泣いて怒って大はしゃぎだった。あと異星人向けの解説もあったので、イエルヴがアイルランドの虫野郎という台詞を覚えていたのもそのせいかもしれない。
「んで、こいつの口癖が最近ヘヴィになりました」
「相変わらず単純なこって」
カリウが横目でイエルヴを見やると、フライもニヤニヤ笑いながら言った。イエルヴが以前マフィア物の映画の影響を受けまくっていたのは仲間内では有名だ。
「違ぇよエレオノーラのオススメがまともじゃなかっただけで俺は悪くねえ」
「そういうところがガキくせえって話だよ」
「うっせぇ」
そんな風にふて腐れるところもガキっぽいのだが。
「でも俺もMcFlyみたいな名前、映画の中だけだと思ってた。まさかこんな身近に実在したとは……」
「ま、珍しいのは確かだな」
「やっぱそうだよな」
名前辞典よりも英語辞典の領域ではないか。そう思って何となく端末の英語辞典を開いてみる。飛ぶだのハエだのずらずらと並んだ最後に、ぽつんとその形容詞はあった。
「"格好良い"?」
「兄さんは格好良いよ」
さも当然とばかりに言ってのける弟の隣で、言われた兄は何とも言いがたい顔をしている。呆れたような困ったような面映ゆいような。
「よっしゃ次は俺だ!」
そんな微妙な隙間を蹴飛ばす勢いでイエルヴが声を上げる。また違った意味で苦笑がこぼれた。
「はいはい。あ、イエルヴってどう書くんだっけ」
「Yelveだよ覚えててくれよ」
「はいはいY・e・l・v・eと。──うん、出ねえ」
「変わった名前だものね」
「あんたに言われたくねぇよ」
イエルヴがむっと眉根を寄せてフォグに言い返した。
先ほどのフライの話ではないが、試しに他言語辞典の検索に掛けてみる。すると今度は名詞が引っかかった。
「何だこりゃ――トルコ語? おまえってそっち系?」
「んなの覚えてねえよ。何か意味あんのか?」
「グリーンフィンチ」
「って何だそりゃ」
「鳥の名前」
ほれ、とカリウは続けて百科事典に跳んだ端末の画面を、見えやすいようにテーブルの中央寄りに滑らせる。と、イエルヴより素早くクリストフ兄弟が横から覗き込んだ。
「ほー、小鳥か」
「全体的に黄色っぽいところがちょっと似てますね」
「はぁっ!?」
グリーンフィンチのオリーヴ色とイエルヴの褐色が、どうやらフォグの中で同じ色合いにくくられたらしい。
「全然似てねえよ、こんなちびっこい鳥! なあ相棒!」
「そうか? 俺は結構似てると思うぜ」
「どこが!?」
「目つきの悪さとか」
「んな!?」
それまでカリウにぐいぐい詰め寄っていたのが一転、弾かれたようにのけぞる。
「そういやこいつも初対面の野郎には誰彼構わずガン付けてたよな、最初はどんな人見知りだと思ったもんだぜ」
「ああ、あれは人見知りだったんだ!」
「バカ言えありゃ相棒につきまとう変な虫かどうか俺が見てやってただけだ!」
「あー、これっくらい小さかったらイエルヴもちったぁ可愛げあるだろうに……」
カリウがため息をつくと、向かいのフライが喉の奥でくつくつと笑った。
そこへ。
「ずいぶん賑やかだね。何の話だい?」
「面白いことなら仲間に入れてくださいよ」
昼を過ぎてもそこそこに賑わっている店内をすり抜けて、奥までやってきたイリーナとグインが呆れ笑いまじりにカリウたちの隣のテーブルに着いた。
「ようお二人さん。だいぶくたびれてんな」
「ああ、今さっき外から帰ってきたところ。三日ぶりにまともな飯にありつけるよ」
「ほう? デカい話があったんなら、こっちにも声かけてくりゃいいのによ。最近面白い任務がなくて退屈してたんだぜ」
早速食いついたフライに、イリーナがげんなりと首を振った。
「残念ながら近場で数だけ多い小物だよ。けど数が本部の観測よりめちゃくちゃ増えてて、とにかく面倒くさいったらなくてさ」
「討伐っていうか駆除でしたよねーあれ。なんかもう岩場にびっしりうじゃうじゃいるし、あいつら餌にする大型生物が寄ってくる前に片付けなきゃいけないし、おかげで日程オーバーするし、ほんともう精神削られた……」
「まったくだよ……もう、こんな時はとにかく肉と酒に限る!」
「そうっすよねー!」
そうして二人揃って憂さ晴らしのように肉料理のオーダーを豪快に飛ばして、時間つぶしとばかりにこちらに向き直る。
「で、さっき何を騒いでたんだい?」
「名前辞典。公開データベースで見つけたんで遊んでた」
答えてカリウはひらひらと端末を振ってみせた。
「ああ、子供の名前考えるのによく使うヤツっすね。でも何で?」
「俺の名前あるか探してみたかったんだよ。三人で思いついたの片っ端から試しても見つけられなかったけど」
折りたたんでいたメモ用紙を取り出して、身を乗り出してきたイリーナとグインの前に広げた。ずらりと書き出された綴りにはことごとく×印が付いてしまっている。
「いろいろ出てきたっすね」
「確かに聞いたことない感じの名前だし、これだけやって駄目ならきっと言葉が違うんだろうね」
「だな。俺も諦めて、他のヤツらの名前検索して遊んでたところだ」
「そっかぁ。中尉の名前も載ってますかね?」
「あるんじゃない。あたしのは普通によくある名前だからね。そっちのヤツらみたいに面白味もないよ」
言いながらイリーナが目で指し示したのはクリストフ兄弟だ。
「面白がられちゃったね兄さん」
「どうせ普通じゃねえよ。せっかくだから普通の名前ってヤツも調べてみろよ」
「おー。──って、おい?」
メモを再度片付けていたカリウの手から、するりと端末が抜き取られる。
「イリーナはギリシア神話の平和の女神様の名前、ロシア語風」
いつの間に忍び寄って来ていたのか、カリウの背後からマードレスが手を伸ばしていたのだ。
「ほら正解」
果たして彼女の言ったとおりの語源が画面には映し出されていた。
元はギリシャ神話の女神エイレーネーだが、他のヨーロッパの言語に広まるときに形が変わっているので、様々な表記と発音が存在する。イリーナというのはロシア語での形のようだ。ロシア語での表記も載っている。
「どうせ平和だの女神だの、あたしには似合わないよ」
「何ふて腐れてるのよ、大好きなお父様からもらった名前でしょうが」
マードレスがくつくつ笑う。
「女神ねぇ……」
すると半信半疑といったていでイエルヴが、カリウの肩越しに端末の画面を覗き込んできた。
「うわ何だこれ文字か!? ――ぐぉっ」
途端、人の耳もとなのもお構いなしにいつもの大声を上げたイエルヴの額を、カリウはすかさず裏拳でしたたかに小突く。
「あ、相棒……ちったぁ手加減してくれ……」
「おまえはいい加減学習しろ」
小突かれた眉間を押さえて口を尖らせるイエルヴに、イリーナは毒気が抜かれたように噴き出した。
「あんたほんとガキっぽいね。ロシア語見るのは初めてかい? ロシア語はそのキリル文字っていうアルファベットで書くんだよ。まあ、あたしも使えるわけじゃないんだけどさ」
「ロシア人はロシア語使うんじゃねえのかよ?」
イエルヴが怪訝そうに目を眇める。
「あら、イリーナはロシア人じゃなくてロシア系アメリカ人よ。お勉強しなかったから使えるのはアメリカ英語だけよね」
「その通りだけど、なんかむかつく」
イリーナがまた睨みつけるが、マードレスはどこ吹く風だ。
「グインは?」
聞いたことあるようなないような微妙なラインの名前だよな、と評したのはフライだ。
「僕はGuinって書くんすけど、たぶんそのままだと出てこないんじゃないっすかね。元々の綴りはGwynだって祖母ちゃんから聞いたことあるっすよ」
「Gwyn? ――おお出た出た、ウェールズ語」
グインの言ったとおりの結果だった。ウェールズ語だからリンと同様に特徴的な綴り方をしているのか。
「意味は?」
イリーナが身を乗り出す。
「白」
「へえ、whiteとは全然違うんだね」
「アーサー王を捨てたグィネヴィア王妃の名前と同じ語源ね。イリーナ、あなたも捨てられないようせいぜい大事に可愛がってあげなさいよ」
「なっ」
「──ありえないっすから!」
マードレスの揶揄にイリーナがまた眉をつり上げた瞬間、割り込んだグインが力いっぱい否定した。
「中尉を裏切るなんて、そんなのありえないっす」
「お、おう? ありがとな?」
「あらあら、可愛らしいことで」
マードレスは白けたと言わんばかりの酷い棒読みで言って肩をすくめる。
それを見てイリーナが、つと意地の悪い笑みを浮かべた。
「そういうシャロンお嬢様のお名前には、どんな素敵な意味がおありで?」
その言葉に、マードレスの本名を初耳だった面々の視線がいっせいに彼女へ集中する。あからさまに面白くなさそうな顔をしたマードレスは、軽く嘆息をこぼした。
「ありふれた普通の名前よ。元は旧約聖書に出てくる地名ね」
検索してみると彼女の言うとおり、砂漠の国にある肥沃な平原の名前が由来だと名前辞典にも書かれている。
それともう一つ。
「"シャロンのばら"?」
「それも同じ。シャロンに咲く花って意味だから」
首を傾げたカリウにもマードレスは面倒くさそうにだが答える。
「なんだ綺麗な名前じゃんか。汚さないように気をつけなよ」
ありふれた名前とは普遍的に好まれる名前のことだ。にまにまと満足そうな笑顔でマードレスを見上げて言ったイリーナは、ちょうど店員が運んできた料理にさっさと向き直ってしまった。
最後はすっかりイリーナに持っていかれてしまったマードレスも、すっかり興が削がれた様子でカリウたちの真後ろの席に落ち着く。数日ぶりにまともな食事だというイリーナたちを邪魔する気はないらしい。
「で? マードレスは何しに来たんだ?」
忍び笑いをこぼして、カリウは彼女のテーブルに移る。
彼女の前にはコーヒーが一つ。以前に安っぽさまでダイナーらしさを再現しなくてもいいのにと酷評していたコーヒーだ。 日が暮れてからの酒席ならばともかく、その名前通りに大衆食堂然としている日中のダイナーにマードレスが現れるのは珍しい。
「別に。あなたたちが集まって騒いでるって聞いたから、ちょっと冷やかしに来てみただけよ」
「要は暇だったのか」
「そうとも言うわね。何か美味しい話ないかしら」
「あったらこんなところで遊んでねえよ」
「さあ、どうかしらね」
見下ろす彼女の目が、すっと細められた。
「──自分の名前が気になるの?」
思わずカリウが肩を跳ねさせると、マードレスの声に含まれる笑みがいっそう色濃くなる。
「でもあれはアメリカで出版された名前辞典でしょ。今のあなたの役に立つとは思えないけど」
「詳しいんだな」
「名前はバカに出来ない情報よ。移民の二世三世だって誰もがイリーナのように祖国を忘れるわけじゃない」
「なるほど」
「カリウの場合そんな本で遊ぶより、あの教会のお姫様か、いっそナギ長官に直接訊いた方が早いんじゃないの」
「マードレスは?」
ヒメリをその名前からお姫様とからかうマードレスは、日本語も多少なりと知っている。ミラでの会話はすべて自動的に各人の母語として聞こえるので、同じ意味の単語でも聞こえる音は別物になる。
「……あなた、」
眉をひそめたマードレスは何かを言いさして、首を小さく横に振った。
「白鯨の搭乗者には日系も日本人も少なくなかったわ。サクラバグループはかなりの大口だったから。あなたもきっと、軍人ではなかったのでしょうね」
「何のことだ?」
「女の勘よ。――名前に何があるというの? 私たちがバラと呼ぶものは、他のどんな名前で呼んでも同じように甘く香るわ」
「シェイクスピア?」
マードレスが諳んじたヒロインの台詞は有名な戯曲にある一幕だ。
「正解。あなたの記憶喪失ってどうなってるの」
「たまたまこないだ見ただけだっつの。それより何でジュリエット」
「意味なんてないのよ」
バカね。ひどく呆れたような声で、なのに珍しくその響きは優しかった。
名前とは呼ぶため呼ばれるための記号だ。
失われた過去の自分を誰も呼ばないのならば、忘れられた名前にも意味はないのかもしれない。
けれど。
「残念ながらエリートの僕でも、ここにある以外の綴りはちょっと思いつかないですね」
すみません。×が付された候補に目を通したHBが悔しげに眉根を寄せる。
「気にするなよ。どうせダメ元だから」
金網の床に座り込んだまま、カリウはひらひら手を振ってみせた。
ブレイドエリア上層の外れにある工事中区画は半端に設置された落下防止網と非常階段があるだけで柵もない。しかし頑丈な金網は暴れたりしなければ足場としては充分な強度があるので、人目につきにくい早朝のこの場所は昼夜を問わない賑やかさから距離を置くことができて、剣の形稽古に打って付けだった。
――が、今朝は気が乗らなかった。ぶれる己の切っ先を見るだけで気が滅入る。
そんな時に、HBはHBの日課の途中だったというのにサボっているカリウを目敏く見つけてわざわざ降りてきたので、カリウも一昨日から続いている名前の話をすることになったのだが。
「マードレスさんの意見には僕も賛成しますよ。あなたの名前はアメリカでは珍しい」
「だよなぁ……」
苦笑まじりのこれは自分でも気のない返事に聞こえた。果たしてHBはわずかに語気を強めて言葉を続けた。
「煮え切らない態度ですね。らしくない。ナギ長官とは普段あれだけ懇意にしているのに、今さら遠慮するのですか」
愛刀を片手に突然ふらりと現れたナギが、お忍びと言いながら堂々とカリウの即席チームに混ざってくるのも、身内ではもう誰も驚かなくなった。
「遠慮じゃねえよ。うん」
はっきり言われてしまった。カリウは手もとに置いていた自分の刀を一瞥して苦笑の色を濃くする。
そもそもカリウが剣道の形を習ったのもナギからだった。単なる戦闘技術としての剣ではなく、武道としての剣だ。
その重量で叩き斬る通常のロングソードより、扱いに癖のある刀の方が不思議とカリウの手に馴染んで感じられたのは、経験があって身体が覚えていたのかもしれない。過去の手がかりと呼ぶにはかぼそいが、エルマからその話を聞きつけたナギは、何が記憶回復のきっかけになるかわからないし、これは日本文化を残すためでもあると言って手ずから教えてくれた。
だから今さら、ナギに遠慮しているわけではない。
ただ、不安なのだ。
HBは訝しげに眉をひそめたが、それ以上は何も言わなかった。
「そういやHBの本名って何だっけ?」
「ヘクターですよ。ヘクター・バートウィッスル」
Hector。調べてみるとギリシア神話の英雄ヘクトールが出てきた。
その語源は、掴む。
「お、なんかHBらしい名前」
「この僕に、相応しからぬ名前がつくはずがないでしょう」
どういう自信だよ。カリウは小さく笑って、つとHBの視線がカリウを通り過ぎてその後ろを見上げていることに気づいた。
かんかんと軽快に階段を打ち鳴らす音はいったん踊り場で止まる。
「──なんだ。今朝はもう終いか?」
次いで面白がっているような、そして子供のサボりを咎めるようなナギの声に思わず、機械の身体にあるはずもない心臓が跳ねたような気がした。
一度だけ入ったことのあるナギの部屋で偶然、カリウはその写真を見た。
そこには今の姿より一回りは若いだろうナギが、黒髪の少年二人と一緒に映っていた。十代前半と思しき少年二人は兄弟なのか似た面影を持っていたが、ナギと親子には見えなかった。
場所は奥に道場が見える屋外の広場で、三人とも私服ではなく剣道着姿だったから、親子ではなく剣道の師弟か何かなのかもしれない。年長の少年が大きなトロフィーを、年下の少年は小さなトロフィーを持っているから、二人が大会に入賞した記念なのかもしれない。
――もし、あの写真に懐かしさを欠片でも感じていたら、きっと楽になれただろう。
相変わらず神出鬼没の軍務長官への挨拶もそこそこに、HBがすぐ自分のロードワークへ戻ってしまったのは、カリウにとって逃げ場を封じられたようなものだった。おそらくHBもそう考えた。
二人だけになって、探るような眼差しを向けてきたナギに打ち込んでこいと言われて断り切れるはずがなかった。
そうして剣を合わせれば、その一合だけで剣筋の濁りを見抜かれた。
「その話なら昨日エルマからも聞いたな。そうか、見つからなかったか」
公開データのリストに名前辞典を見つけて興味を持ったこと。だが自分の名前らしき項目は仲間で寄ってたかって調べても見つけられなかったこと。洗いざらい白状して返ってきたナギの相槌がまるで、やはりとでも言うような響きに聞こえて、カリウは手の中でメモを握り潰す。
「……長官は何か知ってますか」
「心当たりがないわけでもない。日本の苗字にはカリウと発音するものがある」
「苗字?」
思わずカリウは目を大きく瞠った。
それは考えたことがなかった。ライフポッドから目覚めたばかりのあの時、エルマに名前を尋ねられて意識にうっすらと浮かび上がった音の連なりは、確かにすべてをすくい上げられたわけではなかったが。
「ああ」
肯いたナギが、新たに取り出したメモにペンですらすらと"狩生"と書き記して差し出した。
「これで"かりう"だ。"かりゅう"と読むこともある」
狩生。少なくとも記憶を失ってからは初めて見るその文字を見つめ、カリウは舌の上でその音を転がす。ナギの発音をそっくり真似たそれは日本語の発音であり、普段よりもくっきりとした発音になった。
「じゃあ長官が俺を日本人かもしれないと思った理由も、この名前ですか」
数ヶ月前、一通り行われた調査で今のNLAにはカリウの身元を特定できる情報が残っていないと結論づけられた時、消沈したカリウの顔をまじまじと見たナギは顔立ちが日系の気がすると言い、さらに日本人なら自分と同郷だと笑った。
「……まあ、そうだな」
少し考えるようにナギが視線を泳がせた。
「俺もナギは苗字だ。ナギ・ケンタロウ。下の名前のケンタロウというのはどうも呼ばれ慣れていなくてな。こそばゆい」
「苗字で呼ばれているのはイソベさんもですよね」
「おお、あの人も名前で呼ばれても気づけんとよく笑っていた」
元サクラバの旧知だからかナギの物言いは気安い。
「そういうものなんですか」
「そういうもんだ」
狩生。真っ白な紙に書き付けられた、その文字をカリウは指先で撫でた。
「俺の」
――下の名前って何ですか?
思わず言いかけた問いかけは、すんでの所で飲み込んだ。
これが自分の名前なのか、この名前を自分が知っていたのか、ちっともわからなかった。
だからそれに縋ってしまうことは、まるで他人の想い出を盗むような気がして、ひどく苦かった。
名前とは呼ぶため呼ばれるための記号だ。
失われた過去の自分を誰も呼ばないのならば、忘れられた名前にも意味はないのかもしれない。
けれど自分の中にある何かには今、名前さえないのだ。
(俺が俺を呼ぶための名前さえ。)
名前ネタ補足。
映画話はミラリアンの元ネタのアレですMcFlyのことです。マ・ノンとE.T.ごっこしたかったモブがいたのでBTTFだって存在するよね!
グリーンフィンチ=和名アオカワラヒワ。目つき悪い鳥。
ロシア語圏はファミリーネームに男性形/女性形があるのですが、イリーナは姓が男性形「アクロフ」のままで女性形「アクロワ」になっていないため、ロシア生まれではないはず。移民の子孫になるはず。
聖書の雅歌2:1のrose of Sharonはチューリップ(原種)説がいいです。昔々のroseという単語はバラという品種ではなく綺麗な花全般を指す感じ。
アバター主人公は過去作と同じくCV関アニキのカリウ(24)です。捏造設定とか、ゆるく繋がってます。この話の最後でもごちゃごちゃナギさん絡めてアバターの過去かもしれないもの書いてますが完全に私の趣味ですすみません。
これ書いててアビスで書いた物を思い出しました。
オリジナルでもレプリカでもない三番目が帰ってきたED後を書いてました。